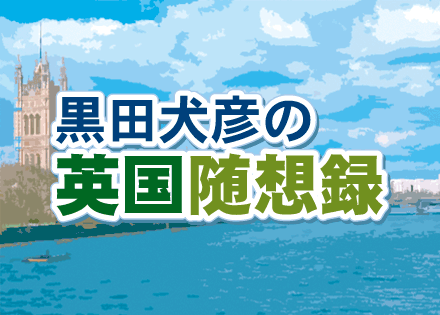![歴史を動かした英国の巨人 ウィンストン・チャーチル《後編》 [Winston Churchill]](/images/stories/great_britons/150806_winston_churchill/ttl.jpg)
暗雲が立ちこめた第二次世界大戦時の英国において、圧倒的リーダーシップで国を率いたウィンストン・チャーチル。
1965年にその戦いの人生に幕をおろし、2015年で没後50年を迎えた。
これを記念し、偉大な英国人として称えられるチャーチルの人生を前編に続きお届けしたい。
1965年にその戦いの人生に幕をおろし、2015年で没後50年を迎えた。
これを記念し、偉大な英国人として称えられるチャーチルの人生を前編に続きお届けしたい。
参考資料:『チャーチル―イギリス現代史を転換させた一人の政治家 増補版』河合秀和・著(中公新書)、『チャーチル』ロバート・ペイン著、佐藤亮一・訳(法政大学出版局)、BBC 『Churchill: When Britain Said No』ほか/上の写真は、ヤルタ会談にて。右からスターリン、ルーズベルト、チャーチル。© US Department of Defense, 1945
●Great Britons●取材・執筆/本誌編集部
■前編のあらすじ…18世紀初頭のスペイン継承戦争で活躍した初代マールバラ公爵を先祖とする名門一家に生まれ、蔵相を務めた父を持つウィンストン・チャーチル。軍人、記者の職を経て、亡き父の跡を継ぎ25歳で政治の道を選択、10年後には内相、後に海相に就任し、出世の階段を登っていた。ところが、第一次世界大戦時のガリポリ上陸作戦での惨敗により失脚してしまう。一度は蔵相として返り咲くも、常に好戦的で議会の和を乱しがちなチャーチルは次第に孤立し、55歳となった1929年以降、閣僚ポストに就くことはなくなっていた…。
揺れる情勢の片隅で

1929年秋に発生した米国ウォール街での株価の大暴落は、悲劇の前兆となって英国に襲いかかる。世界中が恐慌の渦に引き込まれる中、米国はニューディール政策を、英国、フランスはブロック経済を実施し、自国の経済を守るための策を展開した。ところが、第一次世界大戦後のヴェルサイユ条約によって多大な領土を失っていたドイツ、また植民地の少ないイタリアは大恐慌の中で有効な手立てを講じることはできず、国民の不満は手がつけられぬほどに募っていく。その状況を打開するための道を模索する中で、両国には、独裁政権が台頭しようとしていた。遠くアジアでも日本が満州事変を起こし、大陸への侵略を開始するなど、世界情勢は揺れていた。
英国内にも不況の波が押し寄せ、失業率は増大。不安定な局面に立たされる一方で、政界で何の影響力も持たず、隅に追いやられていたチャーチルの攻撃の対象になったのは、インド独立運動の指導者マハトマ・ガンディー(Mahatma Gandhi)だった。
時代遅れの帝国主義者
18世紀半ばから続いていた英国の支配に反発し、インドでは独立運動が盛り上がりを見せていた。これに対し、インドを帝国の栄光と力の証とみなしていたチャーチルは、インドを手放すことは自分の両手両足をもぎ取るようなものと考え、ガンディーへの嫌悪感を公言しては頑に独立を反対。英政府はすでにインドに自治権を与えることを約束しており、実現するのはタイミングの問題だったにもかかわらず、それでも執拗にインド独立運動を攻撃した。こうした大英帝国の栄光に固執するチャーチルの主張に耳を傾ける者はほとんどおらず、古い考えにとらわれた政治家の戯言として受け止められるのが関の山だった。もしも第二次世界大戦が勃発しなければ、チャーチルの政治生命はここで終わりを迎えていたかもしれない。しかし、チャーチルがガンディーに熱を上げる中、アドルフ・ヒトラー(Adolf Hitler)の登場により、事態は変化を見せはじめる。

この動きに対し各国は警戒し、ただちに策を講じるべきだった、と歴史を学んだ後に語ることは簡単だ。しかし、例えば当時の英国は事情が異なった。英国では、第一次世界大戦は帝国主義がもたらした戦争だったとの考えが首脳陣の頭の中にはあった。植民地政策を先頭に立って推し進めた英国は、帝国主義が生んだ大戦の責任をドイツに押し付けたという罪の意識を感じており、不平等な条約を取り払う、つまりドイツの要求をのむことで和平が実現されると信じていたようだ。世論においても「軍縮を通じて平和を」との風潮が強まっていた。
この状況を「平和の危機」と呼んだチャーチルは、再軍備を許せばドイツが再び大戦前のように振る舞うようになることを危惧。勝戦国である英国が軍備を強化することによって平和が保たれると、声高に主張し続けた。しかし常に好戦的なチャーチルの発言は国民の理解を得られないばかりか、議会内でも相手にされず、時代遅れで、他国を挑発する政治家と見なされていた。
だがヨーロッパ内に漂う不穏な空気は刻々と変化していく。国際連盟から脱退したドイツがヴェルサイユ条約の破棄を宣言すると、1936年3月、ヒトラーは大きな賭けにでる。英国、フランスが戦いに踏み切ることはないと読み、ドイツ西部のラインラントに進駐。そこはヴェルサイユ条約で非武装地帯に定められた場所で、英仏からの激しい批判が浴びせられてもおかしくはないはずだった…。ところが、第一次世界大戦の惨禍を忘れていなかった英仏はこれを黙認する。時の英首相スタンリー・ボールドウィン(Stanley Baldwin)の支持は急落、ヨーロッパがきな臭くなる中でチャーチルを求める声が日増しに高まっていった。
国が必要とした、唯一の男

チャーチルの不吉な予感は的中する。ヒトラーにとって協定など何の意味も持たず、一方的に破棄すると、チェコの残りの部分に侵攻。英国にとって屈辱的な裏切りといわざるを得なかった。
チャーチルの警告を聞き入れず、最後の最後まで平和的解決の道を模索した政府だったが、1939年9月1日、ドイツがポーランドに襲いかかると、英国の名誉にかけてドイツに対し宣戦を布告。首相チェンバレンはラジオ放送で「私の政治生活を通じて求めてきたもの、信じていたもの、すべてが破滅してしまった」と語り、第二次世界大戦の開戦を告げたが、この演説は国民の心を暗くするだけだった。
その頃には、デイリー・テレグラフ紙、ガーディアン紙、デイリー・メール紙などの全国紙がこぞってチャーチルを支持する記事を掲載。時代遅れの烙印を押されていた彼は「英国で最も信用されている政治家、安全の番犬」と呼ばれるまでに支持を高めており、当然のように海相の地位を得た。
さらなる権力を手にする機会はすぐに訪れる。
ドイツ軍の傍若無人のふるまいはエスカレートし、デンマーク、ノルウェーに侵攻。英仏軍は後援部隊を派遣するが、すでにノルウェーの飛行場はドイツ軍の手中に収められ、後手に回った陸海軍は身動きがとれなかった。作戦全体としても計画と準備が不足しており、失敗は誰の目にも明らかだった。第一次世界大戦時のガリポリ上陸作戦の大失策の例にしたがえば、罷免されるのはチャーチルのはず。ところが、この失敗で責任を負うことになったのは首相チェンバレンだった。
次の首相には誰が就くべきか、その討議がもたれていた1940年5月10日の朝、ドイツ軍がオランダ、ベルギーに侵攻したというニュースが舞い込んできた。この非常事態の中、ヒトラーを容赦なく打ちのめす戦いを指揮できる人物といえば、屈することを知らない男、チャーチルをおいて他に考えられなかった。
ロンドン地下の閣議室
Churchill War Rooms
第二次世界大戦時、空襲に備えて設けられた閣議室がホワイトホールの地下にあり、現在、博物館として一般公開されている。チャーチルの寝室=写真下、キッチンなど、決して快適ではなかったであろう地下での生活を垣間見ることができる。チャーチルの生涯を紹介する展示もあり。
Churchill War Rooms
Clive Steps, King Charles StreetLondon SW1A 2AQ
Tel: 020 7930 6961
www.iwm.org.uk/visits/churchill-war-rooms
入場料:大人18ポンド、5~15歳9ポンド
※ウェストミンスター駅から徒歩3分。
「あらゆる犠牲を払って」
「I felt as if I were walking with destiny. 私は運命とともに歩んでいるかのように感じた。私のこれまでの生涯がすべて、この時、この試練のための準備に他ならなかったと感じた」
戦局の悪化はあまりにも著しく、5月から1ヵ月のうちに、オランダ、ベルギー、そしてフランスまでもが次々にナチスの手に落ち、降伏が宣言される。6月にドイツの勢いに乗じてイタリアも参戦を決めており、英国はただ一国でヒトラー率いるドイツに対峙しなければならない立場におかれてしまった。
英国の敗北もそう遠くはない…。国民の間に緊張が走る中、首相チャーチルはラジオ放送を通して、国民を繰り返し鼓舞した。
「英国の戦いが今や始まろうとしている。われわれ英国人の生命、わが国の諸制度、わが帝国の長い歴史はそれにかかっている。それ故にわれわれは心を引き締めて各人の義務にあたり、もし大英帝国とその連邦が千年続いたならば、人々が『これこそ彼らのもっとも輝かしいときであった』と言うように振る舞おう」
彼の演説は、戦時中でなければ聞くほうが恥ずかしくなりそうな大げさな言葉に満ちていたが、ラジオを通し、最悪の事態を告げながらも、たじろぐことなく堂々と語るリーダーの言葉は、英国民の気持ちを、前に向かわせたのだった。
本土を襲った航空戦
フランスを手に入れたことで、英国本土への空爆が可能になると、ドイツ軍は8月に入り、軍事施設を中心に攻撃を開始。9月にはロンドン上空から、激しい襲撃を展開した。のちにバトル・オブ・ブリテンと呼ばれるようになるこの戦いにおいて、繰り返される空爆に備え、ロンドンの人口の半分は地下にもぐり、残りの半分は郊外に疎開。チャーチルをはじめ戦時内閣も地下の防空壕に閣議室を設けて、指揮にあたった。戦闘機、パイロットなど、数において劣っていた英国だったが、チャーチルに鼓舞された市民の義勇兵も参加し、軍民一体となり奮闘した結果、ヒトラーは英国上陸作戦を断念。ドイツが矛先をソ連へと変更したことで、チャーチルはそれまで敵対していたソ連との団結を訴え、援助に着手した。
戦時中、国防相として陸海空軍3軍を総括したチャーチルは、軍人、戦争の専門家を自任し、大胆で独創的な作戦を生み出した。バトル・オブ・ブリテンの切迫した事態にあっても、大陸での奇襲攻撃などの計画を次々と練りあげ、これに反論できるほどの戦略家は、ほとんどいなかった。
チャーチルの見事な統率ぶりは、1940年8月初めの世論調査に如実に現れた。首相支持率が88%に到達、政党を問わず、国民から圧倒的な支持を集めた。
大戦中盤では、アジアにおける英国の帝国主義の象徴ともいえた植民地シンガポールが陥落し、同時期に北アフリカ戦線のトブルク(リビア北部の都市)も失ったことで英国は大きな痛手を受け、チャーチルに対する批判が強まったこともある。だが反発も正面から受けて立ち、信任投票を難なく終えている。70歳にさしかかろうとしていたチャーチルは精神面でも体力面でも衰えを見せるどころか朝8時から翌朝3時まで働き、積極的な作戦を要求。戦いが長引くにつれ、ときに時計やタイプライターの小さな音さえも不快に感じ、乱暴で気の短い性格が顔をのぞかせるなど独裁的に振る舞うこともあったが、大戦を通して世界各地を飛び回り、英国の勝利に尽力した。
米国参戦による勝利と崩壊
英国を守るため、打倒ヒトラーを掲げて昼夜を分かたず職務に当たったチャーチルだったが、大戦中の約6年間で、世界における英国の地位は徐々に衰退した。そのカギを握ったのは、チャーチルが頼りにした米国だったことは皮肉な話だ。バトル・オブ・ブリテン以降、ヨーロッパ戦線がソ連にまで伸びた一方、北アフリカではイタリア軍と英軍による戦闘が繰り広げられ、さらに遠くアジアで勢力を伸ばしていた日本がドイツ、イタリアと同盟を結ぶなど戦いの規模は拡大していた。勝利のためには米国の参戦が不可欠と考えていたチャーチルは、頻繁にルーズベルト米大統領と連絡を取り合い、親密な関係を構築。開戦からルーズベルトが亡くなるまでの5年半の間にチャーチルからは1000通以上、ルーズベルトからは700通以上の信書が送られた。
開戦当初は米国は孤立を貫いていた。だが、勢力を増す日本を警戒して、米国が厳しい経済制裁を科したことで、日本は米海軍の拠点があった真珠湾を攻撃。これが米国参戦の決定打となったのは歴史の知る所だ。真珠湾攻撃の報を聞いたチャーチルは、英国の勝利を確信。その日は久々に深い眠りについた。
実際に、米国の参戦によって英国が勝利を手にしたことは言うまでもない。しかし、英国は米国から武器の援助を受ける代わりにジャマイカ、バミューダなどカリブ海にある英軍事施設を米国が使用することを認めた結果、世界における英国の軍事的優位は米国へと移っていく。「どんな犠牲を払ってでも戦い抜く」と宣言したチャーチルが犠牲にしたものは、大英帝国そのものだったのである。
1945年に入り、ドイツの敗北が確実になると、4月にヒトラーが自害。5月7日にドイツ軍が降伏し、ヨーロッパにおける戦いは終わりを迎えた。

写真右:1945年5月8日、バッキンガム宮殿で国民からの大声援を受けた後、国会議事堂でも集まった国民の前に姿を現したチャーチル。お決まりのVサインを見せ、国民とともに勝利を祝った。© IWM
チャーチルは、影響力のあるうちに総選挙を行うことを決め、7月、10年ぶりの選挙が実施された。この『戦い』でも自分の勝利を信じて疑わなかったリーダーに、思わぬ結果が待ち受けていた。
惨敗した戦いのヒーロー
選挙結果へと話を進める前に、当時の英国の状況に触れておく必要がある。ヨーロッパにおける戦いでは勝利を手に入れたものの、軍事的、経済的優位を米国に譲ったことは先に触れた通りだ。海外領土の多くを失い、債務は膨れ上がるなど、栄華を誇った大英帝国の輝きは損なわれていた。失業者が街にあふれ、国民は、住宅、完全雇用、社会保障に高い関心を寄せていた。戦いに夢中になった貴族出身のチャーチルには労働者層の暮らしが想像できなかったのかもしれない。街に張り出されたチャーチルの選挙ポスターには、好戦的な彼の顔と、対日戦争を終わらせることを念頭においてか、「彼の仕事を終わらせる手助けを」の文字。一方、労働党のポスターには、笑顔の労働者を描いた親しみやすいイラストに、「未来のために」「幸せのために」といった気持ちを明るくさせるようなキャッチコピーが施されていた。戦争に疲れ果て、普通の生活を願う国民の心に寄り添ったのは、戦いを終わらせるというチャーチルの唱える使命よりも、労働党党首クレメント・アトリー(Clement Attlee)の描く未来だったのだ。
さらに、選挙活動中の演説では大きなミスを犯す。社会主義を嫌悪するチャーチルは、これまで挙国一致内閣でともに国のために力を合わせてきた労働党を、ナチス・ドイツの秘密警察「ゲシュタポ」になぞらえたのである。戦いのヒーローは一瞬のうちに「三流の政治家」に成り下がってしまった。
選挙の結果は労働党の獲得議席数393に対し保守党213、労働党の圧勝だった。

写真右:1945年に開かれたポツダム会談では、第1回はチャーチルが国を代表して出席したものの、2回目以降は新首相アトリーにその役目が移った。左から、アトリー、米大統領トルーマン、ソ連書記長スターリン。© US National Archives and Records Administration
権力の座から降りたとき

1951年に再び保守党が政権を握ると、76歳を迎えていたチャーチルは政権の長として2期目をスタートさせる。労働党がもたらした「社会主義の重圧」から国民を解放することを公約に掲げていたが、新政権の政策は、前労働党政権が行った政策を大きく受け継いだもので、チャーチルは以前のような勢いを失っていた。翌年、ジョージ6世が崩御し、代わって即位した25歳のエリザベス女王の横に立つチャーチルの姿はひどく衰えて見え、ひとつの時代が終ったことを国民に印象づけた。
在位中、ガーター勲章が授与されると、今度はこれを素直に受章し、チャーチルの名には「サー」がつけられた。だが、平和な社会のなかで、何をすべきか、彼自身が目的を失い、80歳のとき、首相の座を後進に譲る決断を下した。
長くこだわった権力の座を降りるとたびたび心臓発作に襲われるようになった。その後も2度の選挙に当選したが、議会に出席することはほとんどなく、気力も衰え、娘に対し「私はたくさんのことをやったが、結局、何も達成できなかった」ともらすこともあった。戦いの連続だった彼の人生は、権力の頂点の座を去った時点でもう終わっていたのかもしれない。
90歳の誕生日はベッド脇のテーブルにウィスキーのグラスを置き、口には葉巻をくわえて一日のほとんどをベッドの上で過ごしたが、新たな年が明けた頃には口数が減り、周囲の誰もがわかるほどに衰えていた。脳卒中により左半身が麻痺すると、次第に呼吸も不規則になり、1965年1月24日、静かに息を引き取った。それは、70年前に最愛の父ランドルフが他界したのと同じ日だった。チャーチルは不思議なめぐり合わせの下、その人生に幕をおろした。
冬の寒さが一層際立った1月30日、セントポール大聖堂での国葬を終えると、遺体はブレナム宮殿の見えるブレイドン教会墓地に運ばれ、チャーチルはそこで永遠の眠りについた。すぐそばには父ランドルフと母ジェニーの墓石が並んでいた。
名言で知るチャーチル 第2弾
皮肉交じりの毒舌トークで人々を笑わせる側面もあったチャーチル。時に憎らしくも感じられる彼の言葉には、機知が詰まった名台詞も多い。その言葉から彼の人物像を探ってみたい。
Lady Nancy Astor : Winston, if you were my husband, I'd poison your tea.Churchill : Nancy, if I were your husband, I'd drink it.
アスター夫人 : あなたが私の夫だったら、あなたに毒を盛るでしょうね。
チャーチル : 私が君の夫ならば、喜んでその毒を飲もう。
※それほど夫人が悪妻だというユーモア交じりの皮肉

アイルランド人は少し頭が変だ。イングランド人になるのを拒むんだから。
※アイルランド人に限らず、他国民よりもイングランド人が優れていることを表現した発言
Personally, I'm always ready to learn, although I do not always like being taught.
個人的には、私はいつも学ぶ準備ができている。教えられるのは嫌いだがね。
Mr. Attlee is a very modest man. Indeed he has a lot to be modest about.
(労働党のライバル)アトリー氏はとても謙虚な男だ。実際、彼には誇るべき点が何もないのだけどね。
A good speech should be like a woman's skirt; long enough to cover the subject and short enough to create interest.
上手な演説というのは、女性のスカートのようでなければならない。
大事な点をカバーするだけ十分の長さが必要だが、興味をかき立てる程度に短くなければならない。
週刊ジャーニー No.893(2015年8月6日)掲載



























 セール情報をいち早くGET!今週のお買得★食料品『TKトレーディング』
セール情報をいち早くGET!今週のお買得★食料品『TKトレーディング』