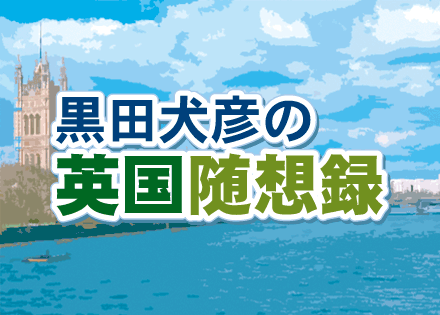日本代表はサモア代表相手にスクラムを押しまくり認定トライを奪った。
2015年9月19日。その日、我々はラグビーW杯史上最大の大番狂わせと言われる衝撃的事件の目撃者となった。前日の18日、英ブックメーカー大手のウィリアムヒルが発表した日本勝利の倍率は34倍。対する南アフリカは1倍。つまり同社は南アフリカの勝利を「ほぼ」もつかない「確定事項」として扱っていたことになる。このことからも日本の勝利がラグビー史上だけに止まらず、いかなるスポーツの歴史においても「とんでもない大事件」であったことが分かる。
1995年に南アフリカで開催された第三回W杯で日本はオールブラックス(NZ)相手に145失点(日本の得点は17)という未曾有の大惨敗を喫した。145失点はW杯史上最多失点として今も記録は破られていない。それはまさに大観衆の目の前で行われた公開処刑さながらの様相だった。この惨劇は今も日本ラグビーファンの心に深い傷跡を残している。同時に日本でわずかに盛り上がりを見せていたラグビー熱に冷や水を浴びせた。今回、ブライトンの会場を訪れた人やテレビで観戦した人で日本を応援する以外の多くは、好ゲームを期待してというよりも優勝候補の一角である南アフリカという名マタドールが一体どのように獲物を仕留めるかを楽しみにしていたはずだ。しかしその日、人々が目撃したのはラグビーW杯史上のみならずスポーツ史上最大級と言われる大番狂わせだった。
知られざる裏側のストーリー
あの興奮から既に1ヵ月。W杯も残すところ南半球の4チームだけとなった。日本は4戦して3勝を挙げながらベスト8に残れなかったW杯史上最初のチームとなり、「史上最強の敗者」というもう一つの勲章を胸にアメリカ戦の翌日、英国を後にした。
過去に2度、W杯を制している強豪南アフリカを、フィクション作家ですら劇的過ぎてあり得ないと敢えて避けそうなエンディングで逆転撃破した日本。中わずか3日で迎えざるを得なかったスコットランドに敗れたのは仕方がないとしても、その後のサモア戦とアメリカ戦はいずれも激戦の末に勝利を手に入れた。南アフリカ粉砕の興奮冷めやらぬ読者の中にはこの2つの勝利を当然と捉えた人も多かったと思う。しかし実際はスコットランド戦を終えた辺りから、日本代表選手たちの体調に異変が起こり、ベスト8進出をかけた後半戦に向けて深刻な危機が迫りつつあったことを知る人は少ない。その危機から日本代表を救ったのは意外にも普段我々のそばにいる、ごく普通の日本人たちだった。今回筆者は幸運にもその方々にお話を伺う機会を得た。代表選手や関係者の方々に、そして何よりこのエピソードが表に出ることを躊躇しながらも遠慮がちにお話をしてくれた方々に迷惑が及ばないように留意しながら、公開できる部分を読者にもお伝えしたい。
指名された小さな店

斉藤由紀雄さんと恵子さん。
舞フードにて。
ロンドン西部のアールズコートに「舞フード(マイフード)」という和食店がある。店を切り盛りしているのは斉藤由紀雄さんとその妻、恵子さんだ。テーブル席4つ、カウンター席5~6の小さな店で開店当初は串カツをメインにやっていたが、次第にメニューが増えて今ではちょっとした居酒屋並の品揃えとなった。気取った料理とは一切無縁。「もつ煮」や「おでん」、「ソーセージのバター炒め」など海外生活が長い人間にとっては魂を揺さぶられるシンプルで飾らない料理が中心だ。店内には「ブルーライトヨコハマ」や「喝采」、それに歌詞がゆるゆるとしたグループサウンズなど、70年代の歌謡曲が控えめに流れる。まるで日本のどこか地方の小さな町の駅前、それもちょっと細い路地を入った辺りにある「一杯飲み屋」といった雰囲気だ。プンプンと漂う昭和の臭いを全身に染み込ませて店を出ると、突然自分が異国にいることを思い出し、ハッとすることすらある。
そんな舞フードにラグビー日本代表チームのケータリングの話が舞い込んだのは昨年の今ごろだった。ただしこの段階ではまだ試合当日の「おにぎり」程度のものだった。今年5月、日本ラグビーフットボール協会の何人かが来英し、選手たちが投宿するホテルや練習場の視察をしてまわった。「ある程度の日本食ならうちでも作れる」と豪語していたブリストルのホテルで実際に日本食を作ってもらった。ところが出てきたものは粥状の米に、茹でただけでツユすらないソバだった。ブライトンのホテルも似たり寄ったり。1次リーグ後半戦の拠点となるウォーリックのホテルに至ってはキッチンも狭く、関係者を含めて50人にも及ぶ大食漢のアスリート軍団を満足させられる環境にない。視察団は焦燥を隠せなかった。そこで急遽、火曜と木曜の週2日を「和食デー」とし選手たちに日本食を提供することを決めた。正式に斉藤さんにケータリングの話が持ち込まれた。
なぜ席数20にも満たない舞フードのような小さな店に依頼があったのか、不思議に思う人もいるだろう。実は斉藤さんはアスリートとの縁が深い。ウィンブルドン選手権の開催期間中にはテニスの選手たちがお忍びで舞フードを訪れ、英気を養うことが多い。また、かつてはゴルフの全英オープン時に会場に設置されたテント内で日本人選手や関係者らに日本食を作って振る舞っていた時期もある。
今はその時の実績を認められ、松山英樹選手の専属シェフとして全英オープン期間中は店を閉めて現地に赴き、松山選手の活躍を陰で支えている。食事だけのことではない。どんな時でも笑顔を絶やさない明るく穏やかな斉藤さんの飾らない人柄が、不安と緊張で身も心も張り詰めがちなアスリートたちにとって最高の弛緩剤となっている。
難航した迎え入れ準備
日本代表には専属の料理人も栄養士も帯同しない。今回、急遽斉藤さんが調理を担当することになったが、アスリート慣れした斉藤さんでもラグビー選手のために調理するのは初めてのことだ。何をどれくらい食べさせて良いのか皆目見当もつかない。
そこで日本に残っていた代表チーム専属の栄養士さんと斉藤さんがスクラムを組むこととなった。斉藤さんが対応可能なメニューを送り、それを元に栄養士さんが献立を組み立てていく。莫大なカロリーを消費するアスリートたちの食事が日頃小さな店で酔客相手に提供している料理と大いに異なることは想像に難くない。さらに斉藤さんを困惑させたのは献立に制約が多かったことだ。最初に駄目出しされたのは鶏のから揚げやトンカツといった揚げ物だ。ラグビーのような激しいスポーツでは当然動物性のたんぱく質が大量に必要となる。作り手側もひたすら揚げていけばいいので比較的楽なのだが、揚げ物は消化に悪いという理由で却下され、ほとんどが炒め物となった。同じ理由でおにぎりに巻く海苔も禁じられた。仕方なく鮭やおかか、それに青菜をご飯に混ぜ込んで握ることにした。外国人選手が苦手だからという理由で梅干は外された。塩は少し強め。

日本ラグビーフットボール協会から贈られた日本酒を持つコーディネーターの神岡綾子さん(左)と斎藤さん。
栄養士さんからの細かい指示を的確に咀嚼して斉藤さんに伝える重要な役目を担ったのがコーディネーターの神岡綾子さんだ。献立を練り上げていくと同時に神岡さんはブリストルのホテルに、期間中にホテル内レストランのキッチンの一部を使わせてもらえるよう交渉を始めた。ところがキッチンを預かるヘッドシェフがこれに難色を示した。誰だって自分の職場に他人を入れるのは嫌なものだ。しかしキッチンが使えないのは斉藤さんにとって致命的だ。神岡さんは粘り強く交渉に当たった。その甲斐あってホテル側からようやく条件付での使用許可が下りた。しかし「食品衛生管理者の証明書」や「保険証」さらに「食中毒を出した場合に一切の責任を自分たちで負うことを明記した誓約書」等の提出が求められた。その数、およそ10枚。神岡さんはこの嫌がらせとも思える要求に懸命にこたえた。その努力が報われようやくキッチンの使用許可が下りた。同時に炊飯器4台、選手たちが余暇を過ごすためのテレビ、ゲーム、その他、米、ふりかけ、納豆の大量入手に神岡さんは奔走した。日本代表を迎える準備はほぼ整った。
50個のおにぎり

常連客と談笑する斎藤さん。
9月1日、日本代表が来英しブリストルのホテルに投宿した。最初の夕食を作るために斉藤さん夫婦がホテルに到着したのは3日のことだった。難敵だったヘッドシェフと対面した。堅物ではあったが本物のプロだった、と斉藤さんは振り返る。一旦キッチンを提供すると決めた以上、頼んだことはどんな面倒なことでも細かいことでも嫌な顔ひとつ見せずきっちりと対応し協力してくれた。斉藤さんは今もこの時のシェフに感謝しているという。嫌がらせなどではなく、高いプロ意識から出た細かい指示だったということも分かった。
ただ、ホテル側が炊いたというご飯を見て斉藤さんたちは目を疑った。それはご飯というものとは程遠いものでサラサラの粥だった。炊飯器の使い方をきっちり伝えたはずだったが、そもそも日本人が普段どういった状態のご飯を食べているか知らない人たちだ。水の量を間違えたのだろうが、仕上がりは惨憺たるものだった。チームマネージャーに言うと「これなどまだいい方です。色々な国に遠征していますが、ご飯に箸を刺したら箸が抜けなくなるような米を出されることもあります」と苦笑した。選手たちが不憫で思わず瞼の裏が熱くなった。斉藤さんたちは急ぎ米を炊きなおした。選手たちはアツアツに炊き上がったご飯を美味い美味いと言いながらおかずもなしにがっついた。
1次リーグ初戦となる南アフリカ戦までの2週間強、斉藤さんたちは週2回、現地に赴きポークソテー、サバやチキンの照り焼き、カジキマグロの蒲焼き、牛丼、カレーといった食事を提供した。さらにグルジアとのテストマッチ(強化試合)の際には実戦同様、おにぎりを一人3個ずつ用意する日々が続いた。
9月19日、南アフリカと激突する運命の日。
選手らの元には斎藤さんが手配した150個のおにぎりが届けられていた。日本代表は関係者を含めて50人。彼らは試合3時間ほど前に消化が良い上にエネルギーへの変換が早いおにぎり2個を食べる。そして試合終了後30分以内にバナナやサンドイッチとともにもう一つのおにぎりを食べる。体力回復のためにすぐに糖質を摂る必要があるからだ。これはサッカーの日本代表と全く同じルーティンだ。クリケットのイングランド代表チームも試合前の食事は必ずパスタと決まっていると聞く。エネルギーの補充に炭水化物は欠かせない。
南アフリカ戦で世界中を仰天させる大金星を挙げた日本代表だが残念ながら23日のスコットランド戦では後半に失速、完敗した。ベスト8進出のために絶対に落とせないサモア戦は10月3日。9日間の空白があった。スコットランド戦に合わせてグロスターまで恵子さんがおにぎりを届けた後、次の投宿先であるウォーリックのホテルに斉藤さんが行くのは9月29日と決まっていた。ウォーリックのホテルはキッチンが小さく、とてもではないが斉藤さんたちが借りられる空きスペースはなかった。仕方なくここから先はアールズコートにある舞フードで調理したものをせっせとホテルまで車で往復5時間かけて運ぶことになった。不思議だがスコットランド戦のあと丸5日間、一度も「和食デー」が組まれていなかった。この5日の間に日本代表選手たちの肉体と精神に異変が起こりつつあった。それは目に見えないゆっくりとした速度で訪れ、選手たちを静かに蝕みつつあった。
選手たちを襲った体調異変
訪問する9月29日を前にして仕込みをしていた斉藤さんの携帯電話が鳴った。チームマネージャーからだった。
「困った事態になりました。選手たちの食が細くなって極端に体重を落としています。エディー(エディ・ジョーンズ:代表コーチ)がもっと日本食を食べさせろとカンカンです。急で申し訳ないのですが今後は毎日来ていただけないでしょうか」。
マネージャーの声には緊張があった。その様子から斉藤さんもすぐに事態の深刻さを飲み込んだ。斉藤さんは急遽その後の店をほとんど閉めることにし、この期間全てを日本代表に捧げることを決めた。
さらに神岡さんから連絡が入り、今後の献立が全て変更されたことが告げられた。エディーから「圧倒的に肉を増やせ」と指示が出たのを受けた栄養士さんが急ぎ作り変えた献立だった。一人につき一食鶏肉300グラム、牛または豚肉300グラムが基準となった。この日から舞フードのキッチンは山積みされた肉と野菜に占拠されていく。
29日午後、宿舎に着いた斉藤さんたちの目に飛び込んできたのは英気を失いかけた選手たちの姿だった。前より少し小さく見えた。しかし斉藤さんたちを見つけた選手たちは山で遭難した登山家たちが救助隊の姿を目にしたかのような安堵の表情を見せ、そして歓喜した。
海外生活が長い読者であれば想像するまでもないだろう。英国の食事が美味いかまずいかの議論を待つまでもなく、朝昼晩と現地の食事が続くのは耐え難い。それがどんなに高級なフレンチであろうと。ましてや日本代表以外では耐えられないであろうとまで言われる世界一過酷な練習を朝から日が暮れるまでこなしている選手たちだ。食事だけが唯一の救いだった。 しかし選手たちは毎食、代わり映えのしないホテルの食事にすっかり飽き、辟易としていた。ホテル側は彼らが作る料理とは別に炊飯器で毎日米を炊いてくれていたが和食と呼べるおかずは納豆とふりかけ程度だった。胃袋が極度のホームシックを起こしていた。次第に食が細くなりエネルギー源である食事の摂取量が減っていった。その結果、一人平均で3キロ近く体重が落ちていた。日本代表にとって致命的で深刻な問題だった。

ベスト8進出の鍵となったスコットランド戦は完敗。
中3日はさすがに厳しいが、それを公で口にする選手は遂に皆無だった。
今大会で日本代表躍進の要因はいくつもあるが、その一つがフォワードの成長だと言われている。例え外国の選手を入れて大型化を図ったとはいえまだまだ世界のラグビー強豪国と比較すると日本は軽量級だ。例えば南アフリカのフォワードの平均体重は117キロ。一方の日本は109キロで8キロの差がある。8人でスクラムを組んだ際、単純計算で言えばその差は64キロ。サモアのフォワードも南アフリカほどではないが平均体重112キロで日本とは3キロの差があった。他国との体重差を補うために日本代表は元フランス代表でスクラムの専門家、マルク・ダルマゾをコーチとして招聘した。ダルマゾは日本人の膝と足首が柔らかいという身体的特徴を早くから見抜き、独自の理論から日本のスクラムを改良。その上でフォワードに誰よりも過酷な練習を強いた。あまりの過酷さに選手たちは悲鳴を上げた。
しかし昨年6月、テストマッチで対戦したイタリアを、気がつけばスクラムでグイグイとめくり上げていた。「強くなった」と実感した。体重差のある南アフリカと互角とは言えなくとも簡単には押し負けないスクラムに辿り着いていた。エディーは大会前「スクラムさえ支配できたら南アフリカに一泡吹かせることもできる」と公言していた。信じる者は少なかったがエディーだけは本気だった。そしてエディーは正しかった。
しかし、ここにきて一人3キロ体重を落としたとなると話は大きく変わってくる。極端に言えばスクラム全体では24キロが失われたことになる。これでは巨漢ぞろいのサモアとはまともに戦えない。29日以降、斉藤さんたちの生活は日本代表一色となった。午後4時までに50人分の料理を山のように作ってはウォーリックのホテルまで届けた。到着後は食事を温め直し食堂代わりに使っていたバンケットルームまで運びビュッフェ形式に盛り付けてからホテルを出発。舞フードに戻るのは毎晩9時を廻った。戻ったらすぐに翌日の仕込みが始まる。翌朝からまた調理をして届けてと、ハードな日々が続いた。「大変なことに巻き込まれた」とも思ったが、斉藤さんたちの姿を見つけた選手たちが「今夜は何かな~?」と言いながら浮かべる屈託のない最高の笑顔に救われた。「想像を絶する厳しい練習に明け暮れているはずなのに会えばいつも明るく楽しそうだった。そして何より礼儀正しい子たちだった」と恵子さんは懐かしそうに目を細める。
日本代表の3分の1は外国出身の選手たちだ。日本食育ちではない彼らはホテルの食事で問題がないように思えるが実際は全く違った。彼らもまたハンでついたようなホテルの食事に飽き、日本人選手同様体重を落としていた。斉藤さんたちが届けるポークソテー(生姜焼き)、カレー、チキンの桑焼き、ニラレバ、すき焼き、和風ハンバーグなど日本で食べ慣れた手作りの肉料理を貪るように掻きこんだ。「選手たちに食べさせてあげて」と大量のウナギの蒲焼を斎藤さんに託す人たちも現れ、選手たちを狂喜させた。斉藤さんたちが食事を届けるようになってからホテル側が用意する夕食はほとんど誰も手をつけなくなった。

体調も精神面も充実。サモア代表と激突。
やがて選手たちはゆっくりと体重を戻していった。エディーにも笑顔が戻った。そして迎えた10月3日。ミルトン・キーンズでのサモア戦直前、選手たちは完全に南アフリカ戦直前の状態にまで体重を戻すことに成功した。それだけでなく再び全身に針で刺せば爆発せんばかりの精気がみなぎっていた。もはや懸念材料はない。試合開始前、いつものように斉藤さんが握ったおにぎり2つを頬張り、ピッチに飛び出していった。
この経験を4年後につなげ
日本代表の挑戦は終わった。しかし彼らはとてつもない置き土産を残してくれた。我々はユーチューブなどの動画サイトのお陰でいつでもどこでも、そして何度でも今回の日本代表戦を繰り返し楽しみ酔いしれることができる。特に世界を驚かせたあの南アフリカ戦は我々日本人にとってどんな素晴しい古典映画や、最新のCGを駆使したスペクタクル映画をも凌駕する珠玉のドキュメンタリー作品となった。
72分過ぎ、南アフリカにペナルティゴールを決められてから最後の逆転トライに至るまで、約12分に及ぶ日本の猛攻は圧巻だ。何度潰されても諦めず前へ前へと突進していく選手たちの姿は国境を超えて世界の人々の心を激しく揺さぶった。何度見てもハラハラし何度見ても日本は勝つ。これから一体何回見ることになるのか見当すらつかないでいる。しかし筆者は今回、偶然にも知ってしまった。あの南アフリカ戦の劇的勝利の瞬間からサモア戦までの間に代表選手たちに起こりつつあった静かなる危機を。そしてその危機から脱するために奔走した名もない人たちの決して派手とは言えないもう一つの物語を。それを知った上でサモア戦やアメリカ戦をもう一度見直すと全ての景色が違って見えてくる。もちろんドラマの主役は日本代表選手たちやエディーをはじめとするチーム関係者たちだ。しかし今回、斉藤さん夫妻や神岡さんからお話を伺うにつけ、我々が到底目にすることがないところで大勢の人たちが日本代表と関わり、そして活躍をそっと支えていたことが分かったことは幸いであった。

日本代表から選手たちのサイン入りユニフォームが届いた。
舞フードにまた勲章が一つ増えた。
4年後の2019年、ラグビーW杯は日本に来る。それはアジアで開催される最初のW杯となる。ホームである以上日本代表が食事の面で窮することはないだろう。その一方、外国の選手団が最も懸念することの一つが日本での食となる。日本の食事は美味しいから問題ないだろうなどと思うのは思い上がりだ。彼らは南北アメリカ、ヨーロッパ、そして南半球という日本と全く食習慣が異なる国からやってくる。予算に恵まれた強豪国であれば専属の栄養士やシェフ、さらには食材等も大量に自国から日本に持ち込むだろう。しかし今回の日本代表のようにそれが叶わない国も多い。人にはそれぞれ原動力となる食がある。いわゆるソウルフードというものだ。長ければ2ヵ月以上の長期に渡ってやってくる海外の代表選手たちが慣れない日本で食のホームシックに陥り、最高のゲームを披露できないような事態があれば世界中のラグビーファンを失望させる。鍛え抜かれた一流アスリートたちが見せるプレーは国境を超えた人類の至宝だ。ラグビーが決してメジャーなスポーツとは言えない日本であるからこそ、万全の態勢をもって宝物を迎えてあげて欲しいと願いつつ筆を置く。
(写真・文/週刊ジャーニー発行人 手島 功)