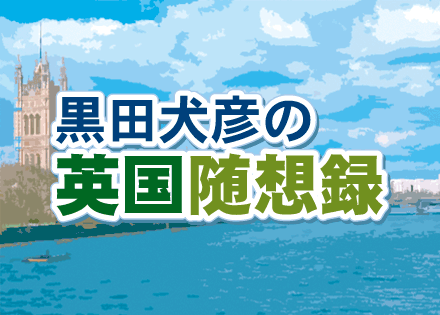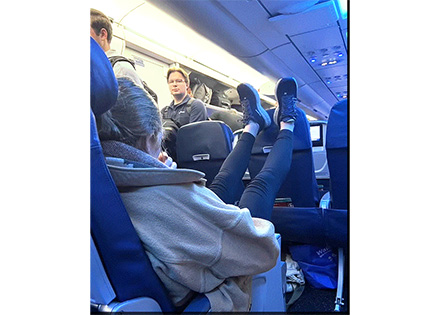どん底の貧困生活
 晩年のデュナン。
晩年のデュナン。
デュナンは虚脱状態のままパリに移り住み、貧民街で細々と暮らし始めた。シャツの襟が汚れたらチョークで白くした。靴には穴が開き、下着も新調できず、ボロボロになっている。往来でポケットにしまい込んだパンを小さくちぎり、少しずつ食べた。
「私はできるだけ切り詰めた生活をして、貧乏という貧乏はみんなし尽くした。(中略)こういう状態にあって私は初めて不幸な人のために嘆くということの本当の意味を学んだのである。自分で本当に悲惨を味わった者でなければ、正しい想像もできない」(回想録より)
デュナンを陰で支え続けてきた母親は、彼がジュネーブを離れた翌年に死去。家族との交流は途絶えていた。頬は痩せこけ、40歳にして60歳すぎの老人のような風貌だったともいわれている。しかしそれでもデュナンは、自身に課した人道活動に対する熱意を失わずにいた。国際仲裁裁判制度による戦争防止と、捕虜の処遇に関する国際会議の提唱を目指し、一人で活動を続けていたのである。1872年、パリで開催された国際会議で講演を行ったほか、ロンドンでも演説を行い、ナイチンゲールから厚い賛辞を受けている。この頃デュナンは、しばらくロンドンに移り住み、プリマスやブライトンなどでも演説を行った。しかしプリマスの演説では、過労と空腹により途中で失神。残りを代読してもらうような有様だったという。以後、心身ともに衰え、ヨーロッパ各地を転々と放浪したデュナンは、1887年にスイス東北部のハイデンの小さな下宿で発見されるまで表舞台には現れなかった。
ノーベル平和賞受賞の栄誉
 スイスの首都チューリッヒにあるデュナンの墓。
スイスの首都チューリッヒにあるデュナンの墓。
1892年春、64歳ですでに介護の手を必要としていたデュナンは、彼が赤十字の創立者であることを知って支援の手を差し伸べた病院長アルテル博士の世話のもと、福祉病院へと身を移す。そして1895年、スイスの新聞記者によって「赤十字の創設者、アンリ・デュナン発見」のニュースが届けられると、再び世間の目がデュナンに向けられた。追われるようにしてジュネーブを去ってから、30年近くの歳月が経っていた。
激励の声や、見舞い金などが届けられ、長らく連絡が途絶えていた友人とも再び繋がった。なかでも、デュナンが放浪時代にシュトゥットガルトで知り合った若き友人、ルドルフ・ミュラー教授は「デュナン財団」を設立。デュナンとともに赤十字発足の経緯を記した書籍の刊行に取り組むなどして彼を支えた。こうして改めて赤十字の成り立ちを世界に伝え、自分こそが「赤十字の創立者」であると人々に知らしめる機会を与えられたのである。
ミュラーはこの本をノルウェーのノーベル平和賞選考委員にも送付した。そして1901年、73歳のデュナンは、栄えある第1回ノーベル平和賞の一人に輝く(フランス人経済学者のフレデリック・パシーも同時受賞)。デュナンはその賞金のほとんどをノルウェーとスイスの赤十字社に寄付し、自身にはごく一部しか残さなかったという。1910年に82歳で静かにその生涯を閉じるまで、平和と人道のために働きかけながら、ハイデンの病院で質素な生活を貫いたのだった。
感受性が強く、思い立ったらすぐに行動せずにはいられなかったデュナン。のめり込みやすい性格で、計画性に欠けるきらいがあったかもしれないが、大胆かつ柔軟な発想力や実行力をもち、自らの行動で示して人々の心を動かした。デュナンの情熱なくしては成し得られなかったことが多々あったに違いない。
一方で、その無鉄砲さから、自ら築いた組織の中で孤立し、そこから身を引いてはまた新たに情熱を注ぐ対象を見つけるということを繰り返した人物でもあったようだ。その突発的、衝動的、感情的な行動が、彼の人生を複雑なものにしたことは疑いないだろう。
だが、どのような状況でどういった仕事に取り組んでいても、デュナンの中で一貫していたのは、幼少期より常に心に抱いていた「人間は人間らしくあるべきだ」という、シンプルでいて実に力強いヒューマニズムの精神だった。そして彼自身もまた、相反するいくつもの要素と常に向き合い、これらと闘うという、非常に『人間らしい』人生を送った一人だったのではないだろうか。










 セール情報をいち早くGET!今週のお買得★食料品『TKトレーディング』
セール情報をいち早くGET!今週のお買得★食料品『TKトレーディング』