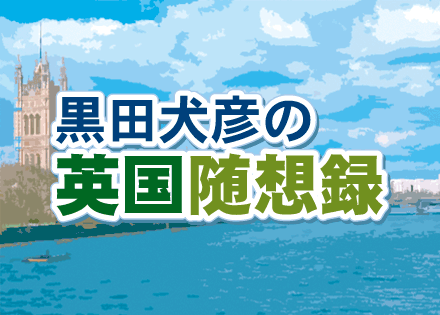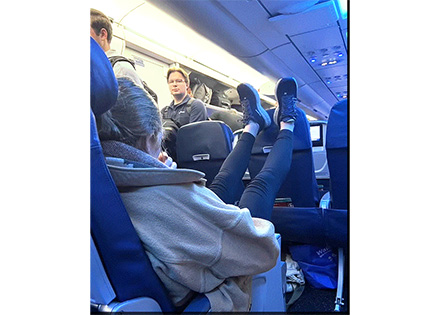ジャンヌ・ダルクの使命 ランスの戴冠式

ランス大聖堂内にあるジャンヌ・ダルク像
人口がパリの10分の1以下の約20万弱、パリ以外のフランスの主要都市リヨンやマルセイユ、ニースなどと比べると町のサイズも小さく地味な印象のランスだが、世界遺産が4つもあるのはこうしたフランスの核としての歴史的歩みが背景にあるからといえる。世界遺産に登録されているのは前述の「ランス大聖堂」、クローヴィスの洗礼に立ち会ったサン・レミ大司教が眠る「サン・レミバジリカ聖堂」とその「博物館(旧修道院)」、そしてルイ12世の治世に建造されたかつての大司教の邸宅「トー宮殿」。これら観光の目玉のほかに、前々号の「シャンパン小事典」でも触れたように、シャンパーニュ地方を代表するシャンパン・ハウス(シャンパン製造メーカー)が軒を連ねており、小都市であるにもかかわらず年間約50万人の観光客を誇る。ランス大聖堂の建設が始まったのは1211年。クローヴィスがかつて洗礼を受けた教会が火災で焼失し、再建されることになったためで、13世紀末にほぼ大部分が完成した。しかし、古くから聖なる都市であったランス、そしてフランス王家の象徴でもあるランス大聖堂は、英仏百年戦争、フランス革命、第一次世界大戦と、常に戦乱、動乱に晒される運命にあった。 百年戦争は、端的には「フランス王国の王位継承をめぐるヴァロア朝フランス王国と、プランタジネットおよびランカスター朝イングランド王国の戦い」とされ、英仏の脈々と続いた戦いと理解されるが、実態はもちろん、数行で語れるようなものではない。ここでは詳細に触れるつもりはないが、当時双方に100年戦っているという自覚もなければ、戦いが始まった14世紀半ばには英仏といった国家としての意識もかなり希薄だったといえる。 イングランドのウィリアム征服王は別名「ノルマンディー公ギョーム2世」であり、西フランク王国に侵入し、のちにノルマンディー一帯を制したノルマン人ロロの子孫ではあるが、フランスで生まれフランス語しか話せない「フランス人」だった。このことから考えてもその後に続くイングランド王が『母国』フランスを常に欲しがり、フランスと小競り合いを繰り返してきたことは容易に理解できる。英仏百年戦争と呼ばれるようになったのは20世紀に入ってからのことで、当初はフランス人とフランス人の覇権争いだったのである。とはいえ、長く領土の奪い合いが繰り広げられる中で両者間に国家としての意識が芽生え、100年を経て終わってみるとフランスとイングランドの国境というものがしっかり出来ていた――、つまり英仏の戦いとなっていたというのが実態のようだ。 この戦争で圧勝を収めるかにみえたイングランド軍に大逆襲を敢行し、戦況を一挙に翻し、終戦のきっかけをももたらしたのがジャンヌ・ダルクである。彼女が歴史に登場した1428年、ランスを含む北部フランスはすでにイングランドの手に落ち、オルレアンが陥落してしまえば南西部も一挙に占領され、仏全土がイングランドに渡るであろうという危機的な状況にあった。彼女はそこに風のように現れ、オルレアンを敵軍から解放し、時の仏王シャルル7世をランスで戴冠させたのである。オルレアンからランスへの道はイングランド軍が支配する地域で、いくつもの戦いを乗り越えねばならず、無謀な挑戦ともいえた。しかし、誰がなんと言おうと、ランスを奪回し、大聖堂で戴冠式を挙げることはフランスの勝利のために必須の条件だったのである。ちなみにジャンヌ・ダルクは、シャルル7世をランスに導くまで「王太子さま」と呼び、戴冠式を終えるまでは国王になったとは認めていなかったことがわかっている。 こうして決死の覚悟で実現された戴冠式は、政治的に驚異的な効果をもたらした。民衆の士気はあがり、王権は強化され、フランスの国家意識はこれまでになく高まる結果となった。しかし、シャルル7世は戴冠後、この救世主に感謝するどころか、煙たい存在として扱うようになる。当時、イングランド軍と同盟を組んでいたブルゴーニュ公国をなんとか味方につけようとしていたシャルル7世にとって、武力で一挙に決着をつけようとしていたジャンヌ・ダルクとは政策上意見が合わなかったからである。かくして、ジャンヌ・ダルクは次第に孤立し、遂にブルゴーニュ軍に捕らえられ、イングランド軍の手に渡った上、宗教裁判にかけられて火刑に処せられる。19歳の乙女のむごい結末であった。









 セール情報をいち早くGET!今週のお買得★食料品『TKトレーディング』
セール情報をいち早くGET!今週のお買得★食料品『TKトレーディング』